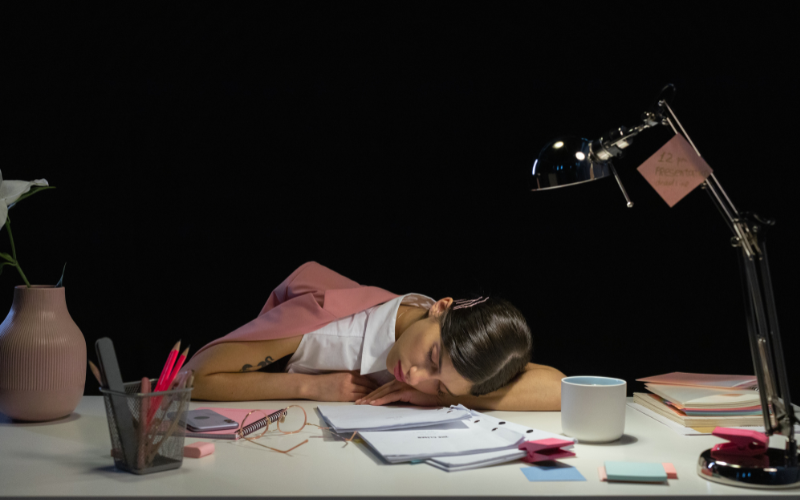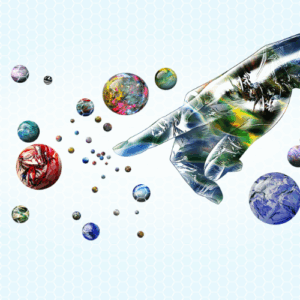センスメイキング理論が、組織を変える鍵になるかもしれません。
ブラック企業と呼ばれるような組織では、なぜ従業員が疲弊してしまうのでしょうか。
その背景には、トップダウンの一方的な「こじつけ」と、それに違和感を覚えながらも従わざるを得ない従業員の関係性があるかもしれません。
しかし、この「こじつけ」は、本来はセンスメイキングの出発点となり得る創造的な行為だと思うのです。
この記事では、センスメイキング理論を軸に、ブラック企業の構造的な問題と、健全な組織へと変革するためのリーダーの役割について、具体的なスキルとともに解説します。
センスメイキングの真髄を理解し、あなたの組織をより良い方向へ導くヒントを見つけてください。
目次
センスメイキングと「こじつけ」の違いとは?組織における納得感
「こじつけ」と聞くと、多くの人はネガティブな印象を持つかもしれません。
しかし、センスメイキング理論においては、この二つの言葉は対立するものではないのと思っています。
センスメイキングは、バラバラになった情報や出来事に意味を与え、他者も納得できる「物語」を紡ぎ出すプロセス全体を指します。
一方、「こじつけ」は、個人的な解釈で物語の「種」を生み出す、創造的な第一歩と言えるでしょう。
重要なのは、その物語が「個人的な納得感」に留まるか、「他者も巻き込む納得感」にまで昇華できるかという点ではないでしょうか。
ブラック企業では、リーダーが個人的な「こじつけ」で生み出した物語を一方的に押し付け、その納得感を他者と共有するプロセスを軽視しがちです。
ここに、健全な組織と不健全な組織の境界線があるのではないかと思うのです。

センスメイキング理論におけるリーダーの役割
センスメイキングを成功させるためには、リーダーが重要な役割を担います。
単に目標を指示するだけでなく、従業員一人ひとりが組織のビジョンに「納得」できるような物語を創り、共有する力が必要です。
謙虚さが鍵を握る「ナラティブ」の力
リーダーが一方的に語る物語ではなく、従業員との対話を通じて共に創り上げる物語、それが「ナラティブ」です。
ナラティブは、単なるビジョンを共有するだけでなく、組織の歴史、価値観、そして未来への希望を包含する力強い物語となり得ます。
健全なセンスメイキングでブラック企業体質を改善
ブラック企業の多くは、トップダウンの指示、一方的な情報伝達、異論を許さない硬直したコミュニケーションが特徴ではないでしょうか。
これは、健全なセンスメイキングとは真逆のアプローチです。
健全なセンスメイキングでは、リーダーは「他者の話を聞く姿勢」や「事実の共有」を通じて、多様な意見を尊重し、共感を生み出す対話を重視します。
これにより、従業員は「やらされている」という受動的な立場から、「自分も物語の一部だ」という自律的な立場へと変化し、モチベーションの向上につながると思います。
マインドコントロールとセンスメイキングの決定的な違い
センスメイキング理論は、しばしばマインドコントロールと混同されがちですが、その目的とプロセスは全く異なります。
- マインドコントロール(影):
外部から操作し、意図した通りに行動させることが目的です。
恐怖や不安といったネガティブな感情を刺激し、一方的な情報で従業員の思考を停止させます。
ブラック企業では、このような手法が組織を支配するために使われることがあるのではないでしょうか。 - 健全なセンスメイキング(光):
内発的な動機を引き出し、自律的に行動させることが目的です。
希望や達成感といったポジティブな感情を育み、多様な意見を尊重する双方向のコミュニケーションを通じて、共に物語を創り上げます。
このように、両者は「人々を動かす」という共通の目的を持ちながらも、そのアプローチは正反対です。
健全なセンスメイキングは、リーダーが一方的に命令する「管理」から、従業員の可能性を「触発」する現代的なリーダーシップの本質と言えるのではないでしょうか。
結論:謙虚なリーダーが拓く新しい組織の形
「こじつけ」とセンスメイキングは、実は創造性と社会性が組み合わさった一つのプロセスです。
リーダーが持つべきは、「こじつけ」の創造力と、他者との対話を通じてその物語を育て上げる「謙虚さ」ではないでしょうか。
この二つの力が結びついたとき、従業員一人ひとりが納得できる強固な物語(ナラティブ)が生まれ、組織全体を前向きな方向に動かすことができるのです。
ブラック企業のような硬直した組織から脱却し、自律的で創造的な組織へと変革するためには、センスメイキング理論に基づいたリーダーシップが不可欠です。あなたの組織は、今、どちらの道を歩んでいるでしょうか。
この記事を書いた人
 山口亨(中小企業診断士) UTAGE総研株式会社 代表取締役
公的支援機関を中心に、長年にわたり中小企業支援に携わる経営コンサルタント。
代表著作に「ガンダムに学ぶ経営学」「ドラクエができれば経営がわかる」がある。
山口亨(中小企業診断士) UTAGE総研株式会社 代表取締役
公的支援機関を中心に、長年にわたり中小企業支援に携わる経営コンサルタント。
代表著作に「ガンダムに学ぶ経営学」「ドラクエができれば経営がわかる」がある。
![]() (@susumu_utage)
:1日3回定期ポスト配信中。朝のニュース解説は必見!
(@susumu_utage)
:1日3回定期ポスト配信中。朝のニュース解説は必見!
【免責事項】
- 掲載情報は記事の公開日時点のものであり、その正確性や完全性を保証するものではありません。
- 内容は筆者の個人的な見解に基づくものであり、効果や結果を保証するものではありません。
- 本ブログの情報を用いて行う一切の行為、およびそれにより生じた損害について、当方は責任を負いかねます。最終的な判断はご自身の責任で行ってください。