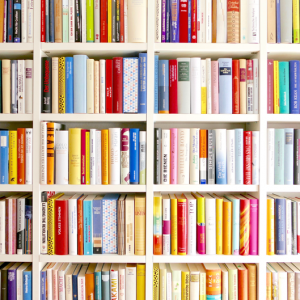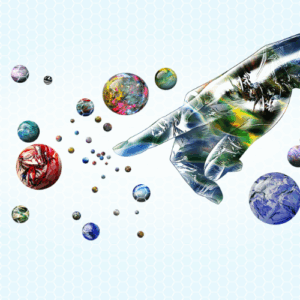突然ですが、センスメイキング理論ってご存じでしょうか?
現代社会のように、情報があふれ不確実性が高い時代には、「正しい答え」よりも、自分自身が納得できる「意味づけ」が必要です。
そのときに重要になるのが、センスメイキング、つまり「腹落ち」することです。
ここで、あの有名な山本五十六の言葉を思い出してみましょう。
「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。」
この言葉、聞いたことがありませんか?
実はこれ、センスメイキング理論と深く関係しているんです。
山本五十六の言葉はセンスメイキングそのものだった
「センスメイキングって、結局何なの?」と思う方も多いでしょう。
簡単にいえば、よくわからない状況で、自分なりに「そういうことか!」と納得して行動することです。
わかりにくい情報や出来事に対して、自分なりに筋を通し、「意味」を「作り出す」
――それこそがセンスメイキングです。
山本五十六のリーダーシップスタイルは、まさにこの腹落ちを重視していたのではないでしょうか。
命令するだけでなく、相手に納得させ、行動を引き出す。
センスメイキングを促すことで、組織全体の力を引き出していたと思うのです。
なぜ今、腹落ちが重要なのか?
なぜセンスメイキング、腹落ちがこれほど重要なのでしょうか?
それは、いくら「正しい答え」を提示しても、人は納得しなければ動かないからです。
「正解」は一つではない時代に、リーダーに求められるのは、「どう腹落ちさせるか」という力です。

センスメイキングの事例:ハンガリー軍の奇跡
ここで、センスメイキングの効果を象徴する有名なエピソードをご紹介しましょう。
アルプスで猛吹雪に見舞われ、絶望的な状況に陥ったハンガリー軍の偵察隊。
彼らはある地図を発見し、「これで帰れる!」と希望を見出し、励まし合いながら進み続けました。
その結果、なんと奇跡的に生還したのです。
しかし、後に判明したのは、その地図は実際の場所であるアルプスのものではなく、ピレネー山脈の地図だったという事実。
つまり、地図は「間違っていた」のです。
それでも、兵士たちは「地図がある」という意味付けによって団結し、行動を続けたからこそ、奇跡が起きたのです。
この逸話は、センスメイキング理論における「もっともらしさ」の力を示しています。
正確さよりも、納得できる意味づけこそが、人を動かし、結果を生み出す原動力となるのです。
まとめ:山本五十六とセンスメイキングの教え
山本五十六の名言と、センスメイキング理論。
両者には、不確実な状況下で人を導くために「腹落ち」させるという共通点が見えてきます。
大切なのは、「正しいか」ではなく、「納得できるか」。
これからのリーダーには、センスメイキングを意識し、チーム全体を腹落ちさせながら導く力が求められます。
興味を持った方は、ぜひセンスメイキング理論について、もう少し調べてみてください。
きっと、山本五十六のリーダーシップが、また違った角度から見えてくるのではないでしょうか。
この記事を書いた人
 山口亨(中小企業診断士) UTAGE総研株式会社 代表取締役
公的支援機関を中心に、長年にわたり中小企業支援に携わる経営コンサルタント。
代表著作に「ガンダムに学ぶ経営学」「ドラクエができれば経営がわかる」がある。
山口亨(中小企業診断士) UTAGE総研株式会社 代表取締役
公的支援機関を中心に、長年にわたり中小企業支援に携わる経営コンサルタント。
代表著作に「ガンダムに学ぶ経営学」「ドラクエができれば経営がわかる」がある。
![]() (@susumu_utage)
:1日3回定期ポスト配信中。朝のニュース解説は必見!
(@susumu_utage)
:1日3回定期ポスト配信中。朝のニュース解説は必見!
【免責事項】
- 掲載情報は記事の公開日時点のものであり、その正確性や完全性を保証するものではありません。
- 内容は筆者の個人的な見解に基づくものであり、効果や結果を保証するものではありません。
- 本ブログの情報を用いて行う一切の行為、およびそれにより生じた損害について、当方は責任を負いかねます。最終的な判断はご自身の責任で行ってください。